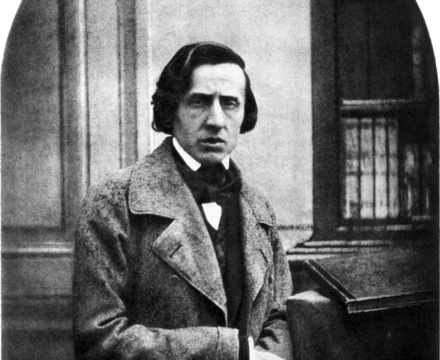最近、AIで作曲された音楽を使ったり、BGMとしてアレンジする機会が増えました。しかし、そこで気づくのが「現行の著作権制度は、現代の音楽の実態に追いついていないのでは?」という疑問です。
たとえば、有名なポップスを弦楽四重奏にアレンジして演奏する──これは教育現場でも普通にあることです。しかし、著作権上は**「元の作者の許可がなければNG」**という扱いになる可能性があります。JASRACに使用料を払っても、アレンジ自体の権利は別扱いです。
さらに、最近ではAIで生成された音楽(例:SUNOなど)を使って、個人が映像やラジオのBGMを作るケースも増えてきました。これらの音楽は、そもそも旋律が曖昧で、雰囲気や音像(音の質感)が中心。つまり、従来の「メロディー中心の著作権判断」が通用しないジャンルなのです。
AI音楽の利用やBGMの世界では、
- 旋律のない音楽に著作権があるのか?
- 雰囲気が似ているだけで著作権侵害になるのか?
- 自由なアレンジにどこまで制限が必要なのか?
……こうした疑問が現場レベルで噴き出しています。
🎯 提案:BGMやアレンジに特化した著作権の新ルールを
従来の楽曲とは異なり、
- 音像・雰囲気中心のBGM
- AIによって生成された構造的な音楽
- 再構成・再演奏を前提としたアレンジ
これらに対しては、「新しいライセンス体系」や「アレンジ許容のルール」を設けることで、音楽文化の自由を守りつつ、権利者も保護できるのではないでしょうか。
BGM専用ライセンス
アレンジ可能ライセンス(Creative Arrangement License)
AI生成物向け使用ガイドライン
こうしたものが整備されれば、もっと多くの人が安心して音楽を創ったり、演奏したりできるはずです。
🧠 最後に:
音楽は、固定された形の再現だけではなく、「演奏し、変化し、解釈する」ことが本質です。
今の制度では、「ちょっと形を変えたら著作権侵害になるかも?」と委縮してしまう場面が多く、現代の創造活動にとって、これは大きな足かせになっています。
アレンジは創造です。
BGMも表現です。
AI時代の音楽をどう扱うか、今こそ見直しが必要ではないでしょうか?